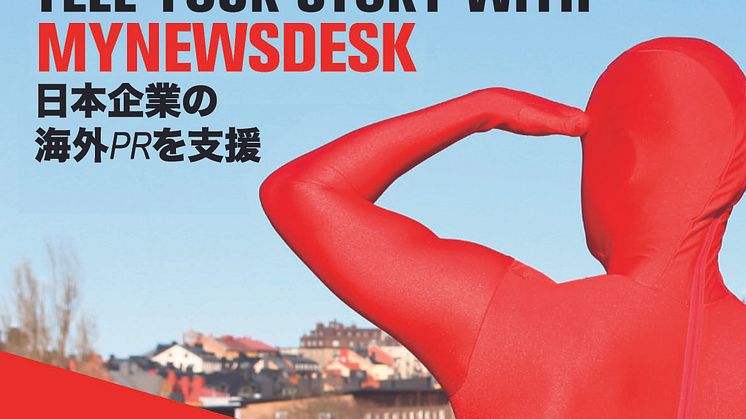ブログ投稿 -
MynewsdeskでグローバルPRを成功させている世界のテック・スタートアップ
こんにちは。Mynewsdesk Japanテックマネージャーの前山です。
VentureBeatやHackerNewsを見ていると面白そうなベンチャー企業がたくさんありますね。私自身、アフリカでテック系のスタートアップをやっていたこともあり、こういった企業には親近感が湧きます。一方、立ち上げたばかりの小さな会社にとってPR、特に海外PRは大変むずかしい部分であり、その痛みも共感できてしまいます。
今回はMynewsdeskを使ってグローバルPRを実践しているテック・スタートアップをいくつか紹介したいと思います。
Readly - 電子マガジンリーダーアプリ
スウェーデンで昨年ローンチしたReadlyは「雑誌のSpotify」とも呼ばれるサービスです。現時点で4000近くの雑誌をタブレットやパソコンなどで読むことができる電子書籍ショップで、月額9.99ユーロの定額月額課金という分かりやすいプライスモデルが特徴です。最近イギリスへの展開を開始したようで、そのことがニュースルームから発信されています。
Magine - どこでもテレビ試聴アプリ
同じくスウェーデンで2011年に創業されたMagineでは、放送中の番組も過去の番組もiPadでいつでもどこでも見られるというアプリを提供しています。現在はスウェーデン・イギリス・スペイン・ドイツの四カ国でビジネスを展開しており、合わせてMynewsdeskを利用して海外PRを行っています。「ドイツでのサービス開始」、「LGとの協力」「Magine利用でTV視聴時間が向上」など、興味深いストーリーが語られています。
Crunchfish - タッチパネルをタッチせずに操作
Crunchfishはタブレットなどのタッチパネルデバイスを、タッチすることなく手のジェスチャーだけで操作できるようになるソフトウェアを開発しています。えっ、と思うようなコンセプトですが、2010年にスタートしたばかりにも関わらず2013年にはRed Herring 100 Europeに選ばれるなど好業績を残しています。ニュースルームの使い方も面白いですね。なんとサイトのトップページに埋め込んでしまうという「その手があったか」といった利用法です。
Rebtel - 格安国際通話アプリ
テック・スタートアップと言うには少し古参になりますが、2006年に創業されたRebtel。Skypeに追いつかんばかりの勢いで成長している国際通話アプリです。そもそも国際性のあるビジネスですのでグローバルPRの必要性も特に高かったのではないでしょうか。ニュースルームはサイトに埋め込まれており、デザインも綺麗に馴染んでいますね。Sendlyのローンチ時にはニュースルームからプレスリリースを公開し、テクノロジー系ネットニュース大手のTechCrunchに取り上げられました。
あなたのテック・スタートアップはどのように海外PRを行っていますか?